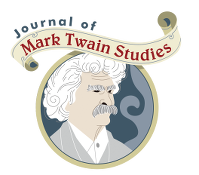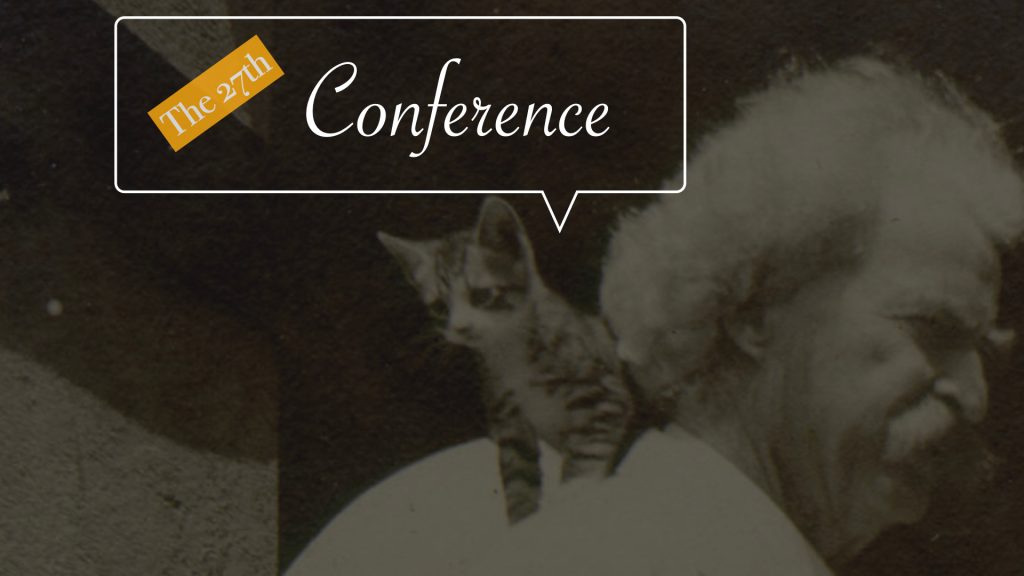
日本マーク・トウェイン協会 第27回総会・大会
開催日:2023年10月28日(土)
会場:東京大学駒場キャンパス 18号館4Fコラボレーションルーム1
会場へのアクセスはこちらを参照してください。 ↓
https://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam02_01_17_j.html
※ 総会のご出欠につきましては、会員のみなさま宛に郵送いたしますニュースレター同封の別紙にご記入いただき、10月14日(土)までに事務局にご返送ください。
*会場と同じ建物でオードブル形式による簡単な懇親会を準備しております。予算は3000円程度を予定しています(インフルエンザやコロナの感染状況によっては中止とさせていただく場合もございます)。
<プログラム>
13:00-13:30 総会
13:30-13:35 会長挨拶
13:35-14:55 研究発表
14:55-15:05 休憩
15:05-17:35 シンポジウム
17:35-17:40 副会長挨拶
18:10 懇親会
個人研究発表 (13:35-14:55)
「動物論」から再考するトウェインの動物物語
――“A Dog’s Tale” (1903)や“A Horse’s Tale” (1907)を中心に
前屋敷太郎(九州共立大学) 司会:筑後勝彦 (富士大学)
Shelley Fisher Fishkin 氏は著書Mark Twain’s Book of Animalsの中で「Twainは、個性豊かな動物が登場する物語を多く残した」(1)と述べている。また彼が動物福祉事業を支援する作家であったことも強調している。
これまでダーウィンの進化論がトウェインの動物観に影響を与えたとされ、先行研究においても実証されてきた。確かにトウェインの動物物語を解釈する上で進化論は不可欠だが、その理論だけでは説明がつかない部分がある。そこで本発表はトウェインの動物物語をより深く解釈する上で有用と思われるコンディヤックやジャック・デリダの「動物論」(機械論や人間中心主義から脱却し動物にも心や魂があるとする)の観点からトウェインの短編作品“A Dog’s Tale”(1903)や“A Horse’s Tale” (1907)等を分析する。そして作品中にある動物論的要素を明らかにすることで、作品理解に動物論が有効であることを実証する。
またトウェインの動物観が当時のアメリカにおいていかに革新的であり動物愛護を推進する現代人の動物観にも通じることを検証する。
マーク・トウェイン『我が自伝からの抜粋』最終章を推理する
――祝賀会スピーチ事件(28年前)と人担ぎエピソード(40年前)との抱き合わせ
井川眞砂(東北大学・誉)司会:里内克巳 (大阪大学)
マーク・トウェイン『我が自伝からの抜粋』は著者が生前 North American Review誌(1906.9-1907.12)に25回連載で公刊した版であり、著者没後にあってはMichael J. Kiskisが1冊の著書Mark Twain’s Own Autobiography (1990)として出版し、Shelley Fisher Fishkin編The Oxford Mark Twain(1996)に収録されたトウェイン自伝である。承知の通りわが国では、本版の里内克巳訳『【連載版】マーク・トウェイン自伝』(2020年)がある。
本報告ではその最終章を取り上げ、晩年のトウェイン考察の一助としたい。この最終章にはトウェインが晩年精力的に取り組んだ自伝の口述2回分(前半は1906年1月11日口述、後半は1907年10月3日口述)が抱き合わされる。雑誌連載ならびに主要新聞日曜版(転載)は、彼の自伝口述作業が軌道に乗り、まさしくその作業進行と並行して、基本的には文字通り『我が自伝からの抜粋』として公刊された。また、上記いずれの口述もAutobiography of Mark Twain: The Mark Twain Papers, 3 Volumes (2010-2015)にその原文が収録されているのは言うまでもない。こちらもわが国では、和栗了他訳『マーク・トウェイン完全なる自伝』全3巻(2013-2018年)がある。
『我が自伝からの抜粋』最終章前半、今や自身も70歳を迎えたトウェインは、読者からの1通の手紙に触発され、封印していた28年前のホイッティア70歳誕生祝賀スピーチ事件(奇妙な出来事)の痛苦な体験をふり返る。その同じ最終章後半に、他人の小犬で人担ぎに成功して3ドル稼いだ40年前のエピソード(愉快なユーモア話)が挿入されるのである。なぜか?失敗した深刻なスピーチ事件を振り返るにあたり、(これまでの作家人生を視野に入れ)みずから吟味するシリアスな話に、なぜ愉快なホークス(hoax) それも創作の要素が多分にありそうな話を抱き合わせたのか?スピーチ事件を振り返るトウェインの視点(1907年10月)から、この問題をしばし推理してみたいと思う。
シンポジウム (15:05-17:35)
マーク・トウェインとユーモア
トウェインは小説家になるずっと以前からユーモリストであった。そもそも、Mark Twainという筆名にしても、今日のお笑い芸人の芸名に近く、完全版『自伝』でも明らかなように、実際、死ぬ直前までトウェインは自身の名前の商標登録を模索している。そして、トウェインは基本的には客商売であるユーモリストであったことで、純文学の作家にありがちな読者を置いてきぼりにした独り相撲の創作の罠に陥ることは比較的まれであったし、人間の愚かさを笑いのネタにしながら、それを自分も含めたどうしようもない人間の一部として愛するような視線を送ることも多かった。バーレスク、スケッチ、旅行記、冒険小説、SF、寓話などなど、トウェインが手掛けたどのジャンルを取りあげても、ユーモアが生命を与えていない作品を見出すことは難しい。では、トウェインはユーモアをいかにして自らの文学の血肉とし、そして社会や時代、他の作家たちはいかにしてこのユーモア文学の巨匠の世界を捉えてきたのか。本シンポジアムでその一端を垣間見られればと思う。 (石原剛)
シーザーは何度も殺される ――トウェインとアーウィンのシェイクスピア・バーレスク連結
講師:宇沢 美子(慶應義塾大学)
バーレスク(burlesque)とはオリジナル(概念・作品)からの逸脱と語り直しという二つの意味でdis-courseが妙味となる手法であるだろう。トウェインはバーレスクを得意とした作家であり、トウェイン流のシェイクスピア・バーレスク作品を複数断片的ながら残した。本発表では1880年代に書かれた『ハムレット』の喜劇版作品(断片)群にみられるbystanderたちの語りを分析し、それと1864年にトウェインがCalifornianに寄稿した『シーザー』のパロディ“The Killing of Julius Caesar ‘Localized’”の二人のreportersの語りとの連関を探ってみたい。後者にみられる、過去の凄惨な歴史的事件を現代アメリカの新聞報道の手法を入れて書き直す、という時代錯誤(アナクロニズム)は、やがてウォラス・アーウィンというliterary journalistによって、ハシムラ東郷物語の一話(1909)に活用されたほか、The Julius Caesar Murder Case(1935)というローマ時代のパピルス新聞Evening Tiber紙のレポータ探偵Publius Manlius Scriboが活躍する長編小説に結実することになる。それはシェイクスピアのバーレスクというよりは、むしろ、シェイクスピアを茶化したトウェインを今ひとつのオリジナルとしたバーレスク作品であった。
トウェインの年齢意識についてのユーモア
――「ベンジャミン・バトンの数奇な人生」に見られるフィッツジェラルドへ影響
講師:渡邉 俊(杏林大学)
1900年、全米で最初の誕生日に関する項目含みの国勢調査が実施されたが、その結果は笑い話のような誤報告だらけだったようだ。人々の誕生日と年齢を結びつける意識が当時は希薄だったことが原因らしいが、結果的にアメリカ社会における年齢意識の向上に繋がった調査であったようである。
トウェイン没後のアメリカは、大量消費を前提とした大衆文化の形成に向かうが、そこには同時に年齢意識や年齢規範が絡んでいた。そんな時代の寵児F. スコット・フィッツジェラルドは、世間の年齢意識たるものを風刺したかのような短編小説「ベンジャミン・バトンの数奇な人生」 (1922) を発表した。フィッツジェラルド自身がTales of the Jazz Ageの中で示したように、この作品はトウェインの人生観をめぐる発言に着想を得ている。これまではトウェイン晩年の悲観主義の影響が指摘されてきたが、本発表では、トウェインの年齢意識に関するユーモラスかつアイロニカルな見解が「ベンジャミン」にどのような影響を与えたのか、フィッツジェラルド自身が読み込んだトウェインの作品や伝記などから検討したい。
国家批判のユーモア――アメリカナショナリズム形成期のトウェインと権威主義体制下の市民の声を比較して
講師:平田 美千子(近畿大学)
米国のナショナリズム形成期に生き、その体現者ともなったトウェインの旅行記、スピーチ、エッセイから自国の体制や権力を批判するユーモアの事例を取り上げ、19世紀後半当時のアメリカナショナリズムの影響下の国家批判のユーモアの意義について考察する。このユーモアの意義の多面的な理解のために、まずは20世紀後半に米国と対峙する政治体制を備えていた旧ソビエト連邦とその支配下にあった旧東ドイツの市民の声に目を向け、対極的状況下におけるユーモアの可能性について検討する。ドキュメンタリー文学作家アレクシェーヴィチの『亜鉛の少年たち』に収録された市民の声と、旧東ドイツ市民によるジョーク事例から、権威主義国家である自国をユーモアを使って批判することが何を意味するのか、ユーモアの自由がない社会や国家に生きるとはいかなることなのかの実態を知ることで、トウェインのユーモアの意義を再発見できるのではないだろうか。
リスペクタブル・ジャーニー ――悪童ユーモアとトム・ソーヤーの運命
司会・講師:石原 剛(東京大学)
悪ガキBartが存在感を放つ国民的テレビアニメThe Simpsonsに代表されるように、アメリカン・コメディには今でもやたらと型破りの悪童が登場する。トウェインが活躍した19世紀後半のアメリカ文学においても「悪童モノ」は人気のジャンルであった。同ジャンルの起源とされるThomas Bailey Aldrichの代表作The Story of a Bad Boy (1869)のみならず、Charles Dudley WarnerやWilliam Dean Howellsといった著名文壇作家たちも悪童モノと目される自伝的少年物語を手掛けている。そして周知のとおり、トウェインこそは19世紀アメリカ悪童文学を代表する作家であった。ただ、彼が描く悪童をよくよく観察してみると、他の文壇作家たちが描く悪童たちとは少し様子が違っている。一言でいえば、トウェインの悪童には、今はほぼ忘れ去られた南北戦争以前の悪童の名残が見え隠れするのだ。本発表では、特に、1850年代に活躍しトウェインにも明らかに影響を与えたユーモリストBenjamin Penhallow Shillaberが作り出した悪童Ikeに注目することで、稀代の悪童Tom Sawyerの変貌の意味を明らかにしたい。