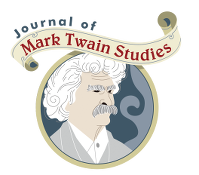開催日:2025年10月25日(土)
開催場所:専修大学神田キャンパス2号館101教室
〒101-8425 東京都千代田区神田神保町3-8
会場へのアクセスはこちらを参照してください。
↓
https://www.senshu-u.ac.jp/about/campus/
*総会のご出欠につきまして、メールでお知らせしましたGoogle フォーム にて10月18日(土)までにご回答ください。
*会場外の飲食店での懇親会開催を予定しております。参加人数を把握するため、メールでお知らせしましたGoogle フォーム にて10月6日(月)までにご出欠をお知らせください。参加される方は、現地にて会費をいただきます。
研究発表(13:30-14:10)
Personal Recollections of Joan of Arc の重層構造
鈴木顕定(東京都立大学聴講生)
Personal Recollections of Joan of Arcは表層のジャンヌの国民的英雄神話と下層のジャンヌと南北戦争批判の重層構造を成している。南北戦争は北のa nationと南のnationsという国のかたちをめぐる、世界史上初の国民国家間戦争であった。ジャンヌ神話が表象するナショナリズムは、北の大義a new nationを表象している。また南北戦争を思わせる砲撃シーン、トウェインの「従軍失敗」経験を投影させたジャンヌと若者たちのシーンが作中にコラージュされている。このように百年戦争は南北戦争の比喩となっているが、表層のジャンヌ賞讃の下には、反戦主義に基づくジャンヌ及び南北戦争批判が長兄ジャック、リシュモン元帥と対照させて展開されている。トウェインの南北戦争批判の諸作品に連なる作品だが、戦死者への哀悼と戦争批判の両立を提起する意欲作である。
ワークショップ(14:15-15:30)
パーシヴァル・エヴェレットの『ジェイムズ』を読む
コメンテーター:木原善彦氏(大阪大学)
パーシヴァル・エヴェレットは、南カリフォルニア大学で教鞭をとる傍ら創作活動に従事する現代アフリカ系アメリカ人作家である。1983年の処女作『ズーダー』(Suder)以来、多岐に亘るジャンルの作品を発表し続けているが、その多くにアメリカの人種を巡る問題意識が通底している。中でも『イレイジャー』(2001)は2023年に『アメリカン・フィクション』(American Fiction)として映画化されたことが記憶に新しい。そんな彼の最新作にして全米図書賞、ピュリツァー賞ほか受賞作が、『ハックルベリー・フィンの冒険』(1885)を下敷きにした『ジェイムズ』(2024)だ。本邦でもはやくも今年6月に木原善彦氏による日本語訳が河出書房新社より刊行され、話題を席巻している。本企画は、翻訳者である木原氏をコメンテーターに迎え、本作を3人の講師がそれぞれの視点から読み解いたうえでフロアに議論を開き、その魅力に様々な方向から光を当てる試みである。(細野香里)
(新)奴隷体験記としての『ジェイムズ』
司会・講師:細野香里(慶應義塾大学)
『ジェイムズ』は、逃亡奴隷ジムの目から見た奴隷制の有り様、そして一人の人間としての主体性の確立と自由を目指す逃亡に至る過程を描くという意味で、伝統的な奴隷体験記の形式を踏襲している。さらにいえば、本作は奴隷体験記の焼き直しではなく、20世紀中葉以降に隆盛した新奴隷体験記(“neo slave narratives”)の系譜に連なる作品でもある。新奴隷体験記とは奴隷とされた人々の主体を再構築することを主眼に、南北戦争前後に書かれた伝統的奴隷体験記を再構築した現代小説を指す。エヴェレットは『ジェイムズ』において、ジムに語りの主導権を取り戻させることで、『ハックルベリー・フィンの冒険』でも特に悪評高い「逃避の章」の問題点を解消し、新奴隷体験記の系譜に連なる作品へと昇華したのである。ジムの主体性獲得のプロセスとして象徴的に扱われているのが、彼の書くことへの欲求と、名前への意識である。そこで本発表では、作中で言及されているウィリアム・ウェルズ・ブラウン、そして言及はないものの奴隷体験記の代表的書き手であるフレデリック・ダグラスの著作を参照しながら、『ジェイムズ』におけるジムの主体性獲得の過程と比較検討し、新奴隷体験記としての本作の意義を考える。
ハックとジムの関係:passing(なりすまし)を補助線として
講師:須藤彩子(中央大学非常勤講師)
ハックは『ジェイムズ』で何度も「ジム」と対峙する。まず、中心となるのは、奴隷を「盗んでいる」のではないかと思い悩む場面である。ジムは、制度や宗教、法律の軸ではなくbad/goodという直観の軸によって判断せよとハックを諭す。この場面こそ、『ジェイムズ』と『ハック』との接合点であり、以後、この場面を基点としてジムとハックとの関係が展開していく。
様々な場面での二人のやりとりには緊張感があり、読みどころを成している。同時に、「ハックは最終的にどう動くのか?」という論点を提示してもいる。ハックの将来を議論するとき、ジムは、「お前は選べる。白人でいられるのだぞ」、「(まさか)奴隷になりすましたいのか?」と問題提起する。人種という境界線の恣意性と危うさを踏まえたうえでどう行動していくことが可能なのか、本作品に多彩なpassing(人種絡みの「なりすまし」)の例が現れることに言及しつつ、ジムとハックのやり取りを追い、ハックの行く末を推論していきたい。
哲学者たちの亡霊
講師:田村亮(早稲田大学非常勤講師)
今回のワークショップのテーマの作品においては、ジェイムズの視点が採用されることでリアリズム小説『ハック・フィン』がよりリアルな形で書き換えられている。『ジェイムズ』第1部後半でジェイムズがハックと別れるところまではおおよそ『ハック・フィン』の物語展開をなぞる形で進むが、ジェイムズの側から同じ出来事が語られることで『ハック・フィン』の無意識ともいえそうな奴隷制の恐怖という主題が補完的に提示されている。ロマンスとも笑いともかけ離れたジェイムズの「冒険」の中で気になるのは、時折差し挟まれる幻想の場面である。たとえば、ジャクソン島でガラガラヘビに咬まれたジェイムズは、熱にうなされながらヴォルテールと議論を交わす。王様と公爵が介入してくる直前には、夢を見てロックを非難する。さらに、第3部の主要部分では、ヴォルテールの登場人物と対話する。この作品を通じてロックやヴォルテールは亡霊のようにジェイムズに付き纏うわけだが、その意味を考察することが作品に接近する方法の一つになるのではないかと思う。
シンポジウム(15:45~18:15)
マーク・トウェインと家族
50歳の父マーク・トウェインの伝記を執筆した13歳の長女スージー・クレメンズは、「わたしたちはとても幸せな家族です」と書き出し、トウェインもその言葉を『自伝』(完全版)で引用している。大局的に見れば、彼は結婚前、厳格な父と優しい母、兄弟姉妹に囲まれて育ち、結婚後は愛情深い妻と3人の娘たちに恵まれ、幸福な人生を送ったと言えるだろう。しかし、評伝研究を通じて彼の人生を紐解くと、必ずしも幸福ばかりではなかった側面が見えてくる。少年時代に目撃した父ジョン・クレメンズの遺体処理、弟ヘンリーや長男ラングドンの早逝、さらには妻や娘たちの相次ぐ死は、いずれも彼に暗い影を落とした。また、家族の死以前にも、親子、兄弟、夫婦、父娘関係においてさまざまな葛藤を抱えていた。作家「マーク・トウェイン」として彼は、家族体験をどのように作品に昇華したのだろうか、もしくはできなかったのだろうか。本シンポジウムでは、彼の家族関係およびその表象を多角的に検討してみたい。(生駒久美)
トウェインと兄――小説・探偵・アボリショニズム
講師:後藤和彦(東京大学)
トウェインが40歳を期に主たる表現形態をノンフィクションから小説へと転じた理由は、作品の素材の追求の果てに、ついに実の父と兄という素材に逢着せざるを得なかったからだと私は考えている。あるいは、兄と父を素材とせねばならなかった必然が作品創作上の一大パラダイムシフトの要因ではなかったか。
父ジョン・マーシャルが作家11歳のときに亡くなり、彼の中で、いわばハムレットの父の亡霊のごとく不可侵の記憶を形成したのに対し、兄オーリオンは亡くなる1897年――長女スージーの死とともに、彼の晩年期を画する事件――まで、南北戦争時の短い絶頂期の直後から、長々と尾を引いて落ちぶれてゆくだけの生き様をつぶさに見つめ続けた存在だった。
ならば――と私は想像を逞しくする――その兄は、彼にとって、逆に彼のすべてを「探偵」の目をもって注視し続けた存在として、ある戦慄とともに認識されていた可能性はないか。そのあてどない可能性についてあてどない話をしてみよう。
マーク・トウェインの誇張された可傷性と「検閲者」
オリヴィア・ラングドンの戯画的イメージ
講師:杉村篤志(立命館大学)
2023年に出版されたBarbera E. Snedecor編集Gravity: Selected Letters of Olivia Langdon Clemensは、275通のオリヴィア・ラングドン・クレメンズの書簡を収録し、マーク・トウェインの妻が全編にわたって自身の声で語る初の著作として、トウェイン研究史上の空隙を埋める重要な役割を果たした。本発表では、オリヴィア・ラングドンの再評価をめぐる1990年代中盤以降のSusan K. Harrisらの議論を踏まえつつ、サム・クレメンズの南部的背景とそれをめぐる発話困難性を念頭に、求婚期の書簡やフィクション作品におけるオリヴィア表象を吟味する。これらを通して、クレメンズが被害者の身振りとともに戯画的に描き続けた「検閲者」オリヴィア像に内包される自伝的問題について再考する。
スージーの「燃やし尽くす炎」――トウェインの後期短編作品を読む
司会・講師:生駒久美(東京都立大学)
トウェインの長女スージー・クレメンズは、1896年に髄膜炎のため24歳の若さで亡くなった。13歳で父の伝記を執筆したスージーは、三姉妹の中でも特に深い愛情の対象であった。トウェインは、長女を「あらゆる面で情熱的」であり「すべてを焼き尽くす炎だった」と評している。スージーの「燃やし尽くす炎」は、彼の生活にも創作活動にも創造的かつ破壊的な影響を与えたのかもしれない。彼女の死後、トウェインは娘を彷彿させる作品を執筆した。注目すべきは、そうした作品において異性愛規範から逸脱する性愛が主題として扱われている点である。本発表は、スージーの書簡に依拠しながら、思春期以降の彼女のセクシュアリティや父との関係性に焦点を当て、彼女の影響がどのようにトウェインの後期短編作品に表出しているのかを考察する。
メディアと亡霊――トウェイン、家族、身体文化
講師:塚田幸光(関西学院大学)
1909年、エジソン社の映像には、庭を歩く白いスーツ姿のトウェイン、そしてテーブルで談笑する彼の家族(ジーンとクララ)が映る。メディアと家族、そして「白い」トウェイン。これらは、何処に接続するのか。
晩年のトウェインが、メディアを積極的に活用し、自己イメージを流通させたことは周知だろう。白いスーツは知性と機知の象徴であり、同時代のユージン・サンドゥに顕著な屈強な身体とは対極である。トウェインは、世紀転換期の帝国的身体に対して、鍛錬や努力を風刺し、運命の前では無力であることを示す。エジソンが記録した二人のカリスマ、サンドゥとトウェインは、奇しくも身体の両極として響き合う。トウェインは、マチズモをずらしながら、喪失を刻む装置としてメディアを捉える。興味深いのは、そこに「家族」が描かれることだ。
本発表では、世紀転換期の身体表象に注目しながら、自身の身体をメディア化し、亡霊化するトウェインとそのテクストの関係性を捉える。そして、身体と家族は如何なる関係性を有するのか。トウェイン晩年のテクスト/コンテクストを見ていこう。